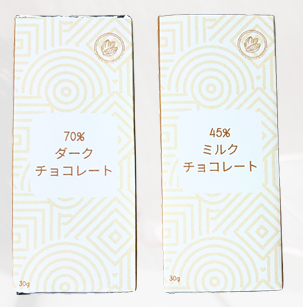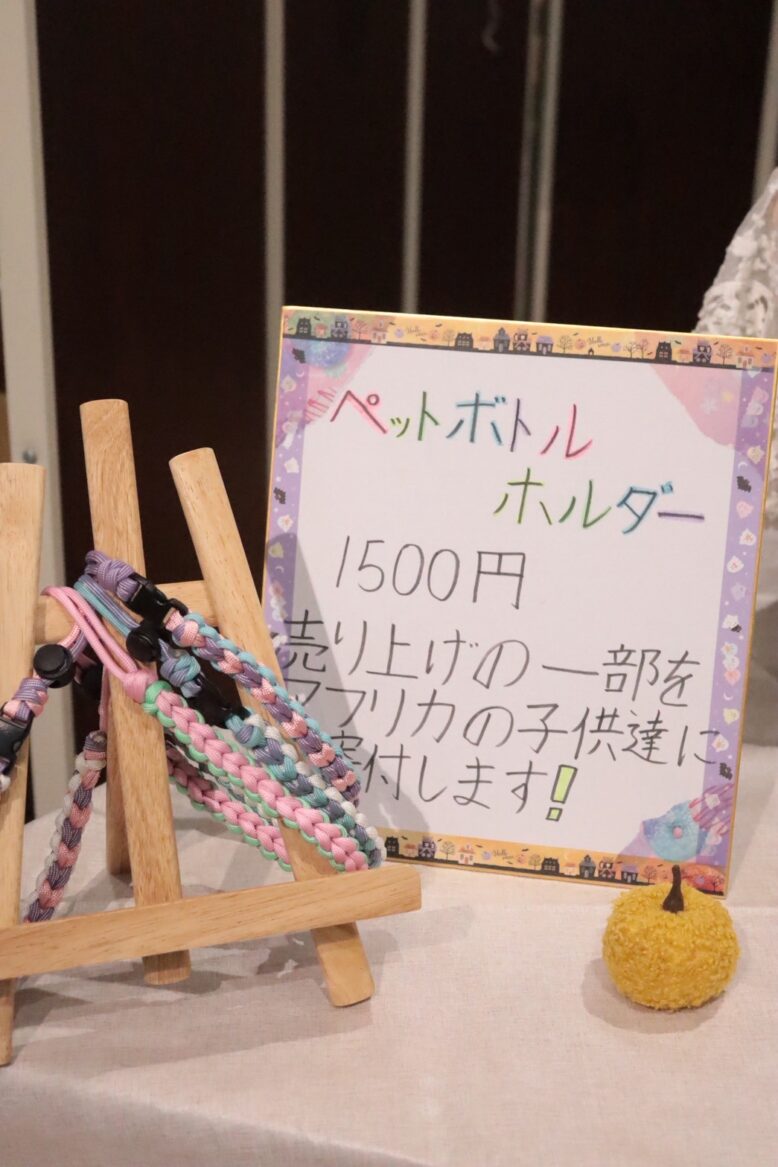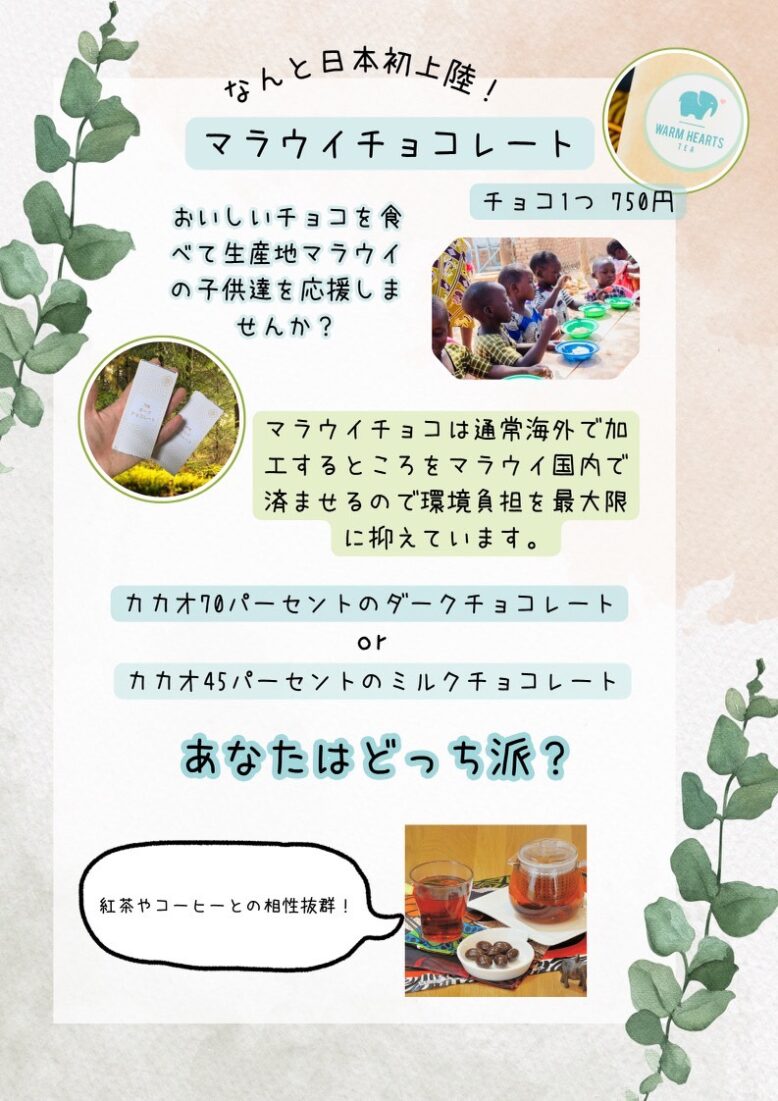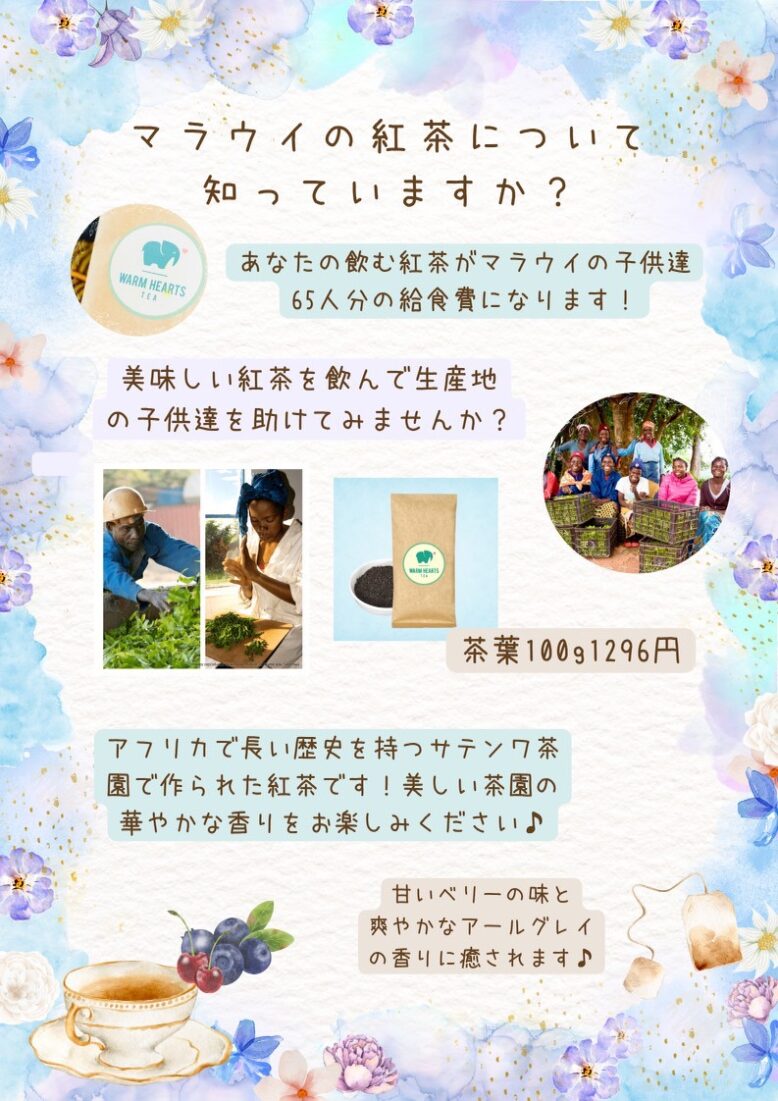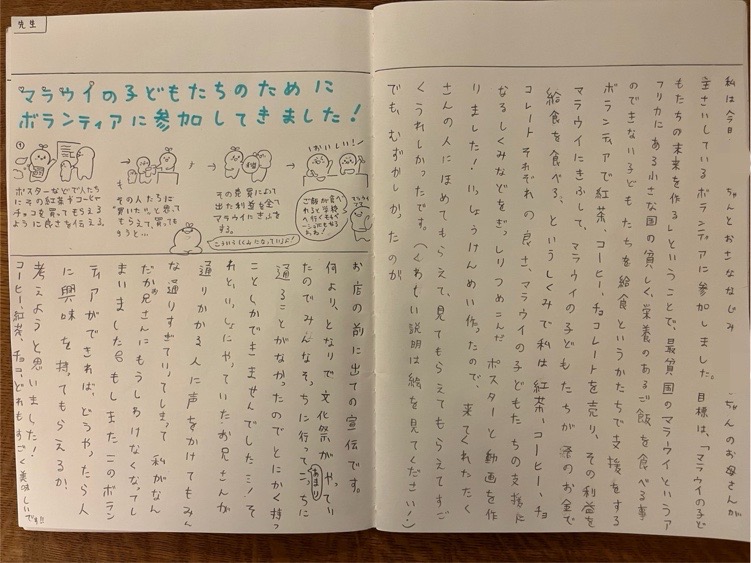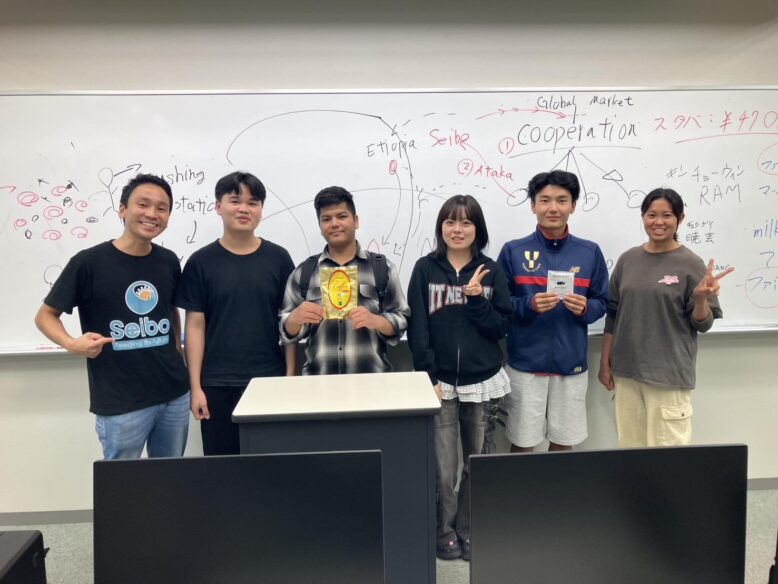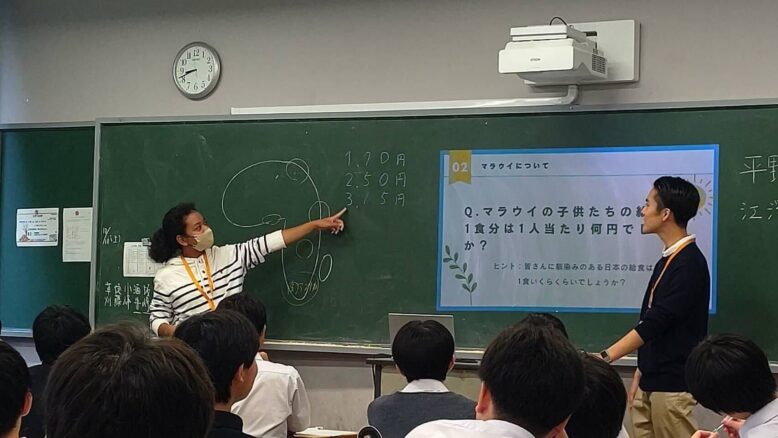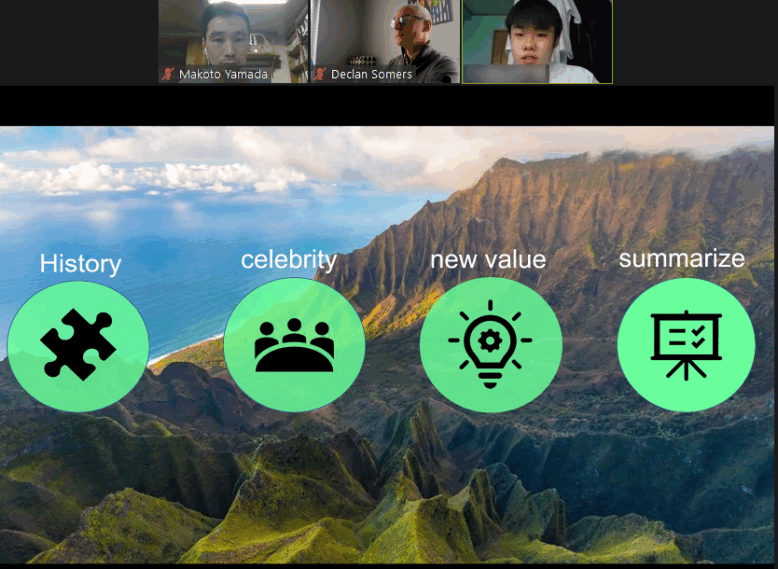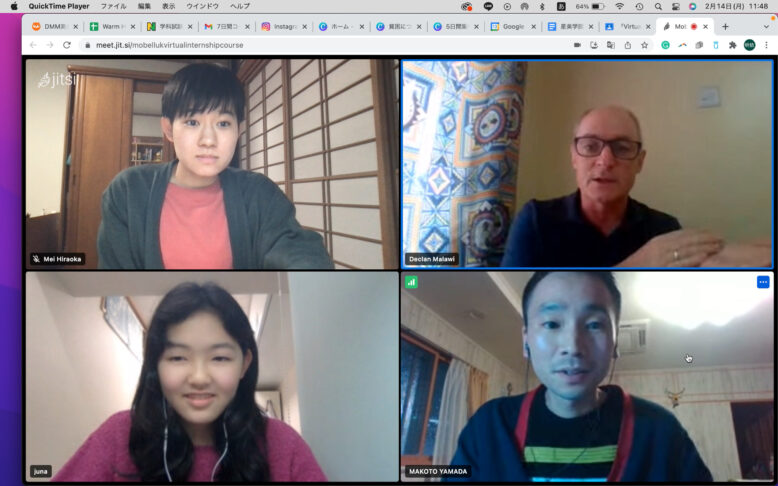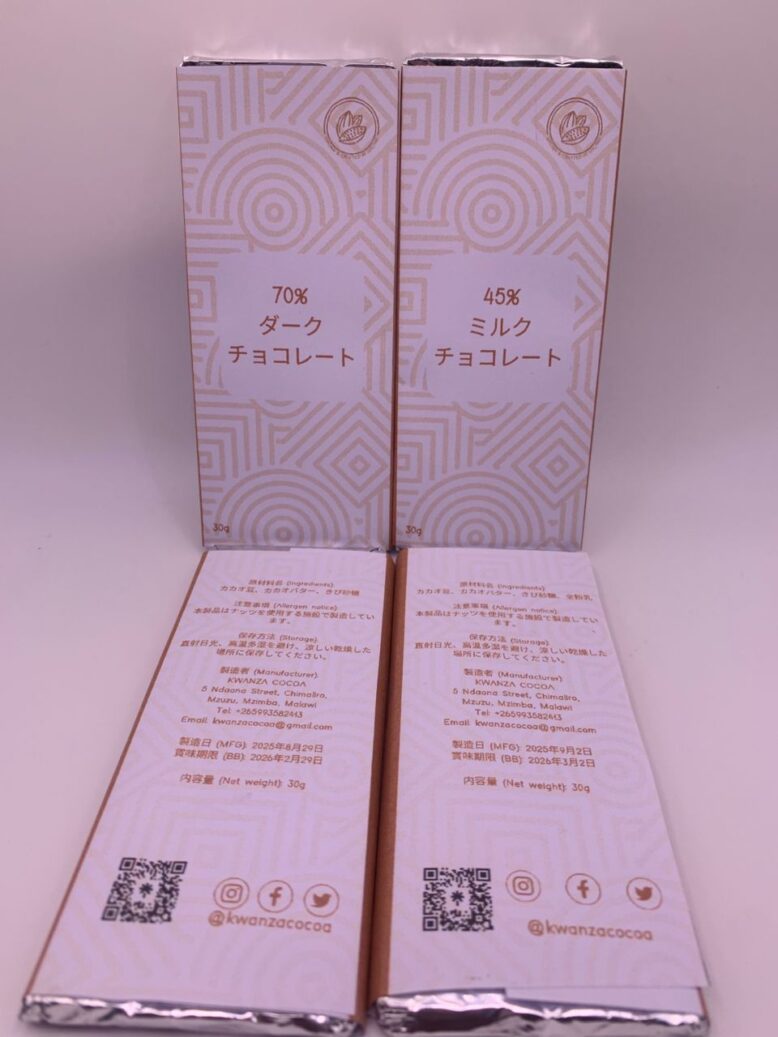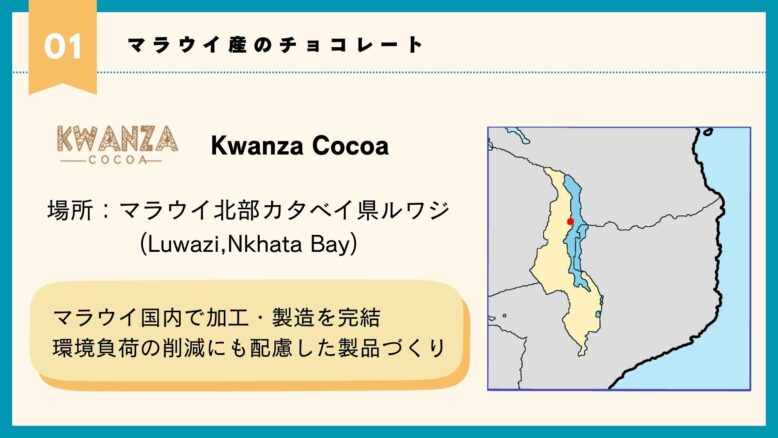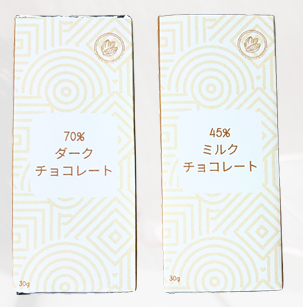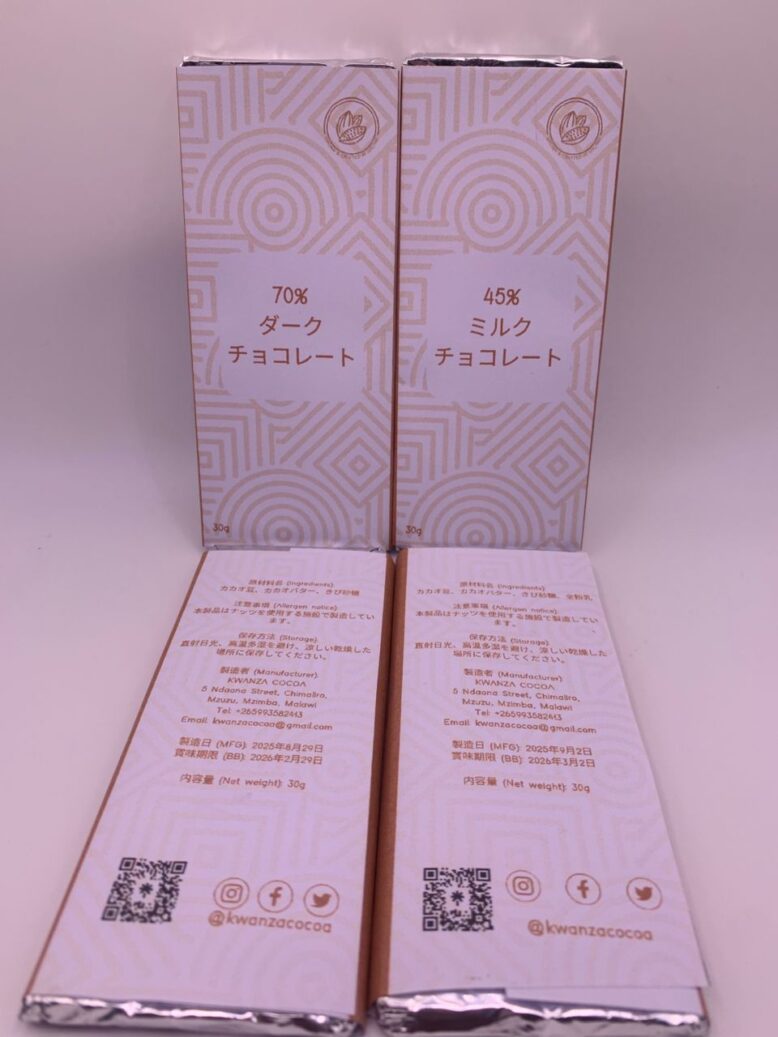
マラウイ北部カタベイ県ルワジで誕生した「Kwanza Cocoa」は、マラウイ初で唯一のビーントゥバー(Bean to Bar)チョコレートメーカーです。
カカオ豆の栽培から加工、製造までをすべて国内で完結させ、環境に配慮しながら丁寧に仕上げられたチョコレートは、アフリカ・アメリカ・イギリスなどでも高く評価されています。
日本では、NPO法人せいぼが初めて輸入し、チャリティ型で販売します!
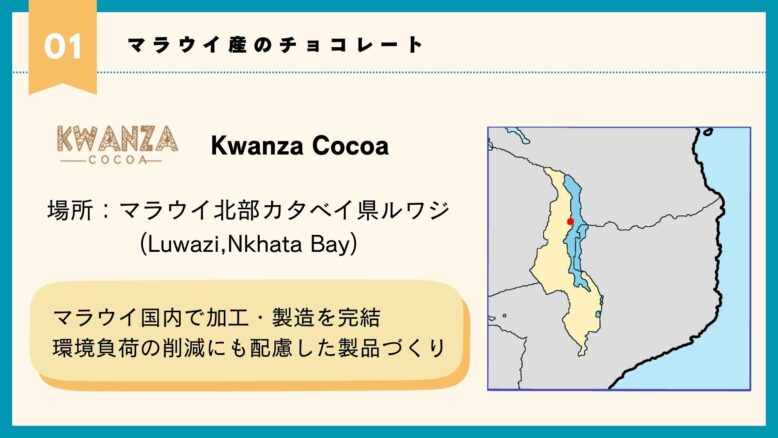
・商品詳細
種類も豊富で、以下のようなものがあります。
-90%ダークチョコレート
-70%ダークチョコレート
-KUMBUZI & SEA SALT(唐辛子と海塩)
-HEMP SEED(麻の実ナッツ)入りダークチョコ
-モカチョコレート
-ミルクチョコレート
以上以外にも、多彩なラインナップを展開。バータイプのほか、ボンボンやスプレッドなども製造されています。
せいぼでは、今回ミルクチョコレートと、70%ダークチョコレートを仕入れています。
農園での取り組みと労働環境
Kwanza Cocoa の特徴は、チョコレートの美味しさだけでなく、働く人々の生活を守る仕組みにもあります。
女性農家への支援
社員13名のうち約6割が女性。さらに、地域の女性農家に苗木や栽培研修を無償で提供し、自立した収入源を確保できるようサポートしています。農園で働く女性たちは、子育てや家事と両立しながら、安定した収入を得ることができます。
持続可能な農業環境
年間3,000本以上のカカオの木を植樹することで、農園の環境を豊かにし、気候変動への耐性を高めています。単なる農作業の現場ではなく、未来を見据えた「学びと実践の場」として機能しているのです。
フェアな労働条件
農園での作業は、児童労働を排し、大人が適正な賃金を受け取れる体制が整っています。農家は「Out-growers Program」を通じて会社と直接契約を結び、安定的にカカオを出荷できる仕組みを持っています。これにより、中間搾取を防ぎ、農家の手取りを確保しています。
環境と人を尊重するチョコレート
一般的なカカオは海外で加工されることが多く、長距離輸送によってCO₂が排出されます。しかし Kwanza Cocoa はマラウイ国内ですべてを完結させるため、環境負荷を最小限に抑えています。
さらに農園見学や試食体験の「Tastings & Tours」では、地元住民や訪問者が農園の仕事に触れ、チョコレートができるまでの背景を実感できるようにしています。ここでは、収穫したカカオを割って発酵させる作業、天日での乾燥、焙煎の工程まで体験可能です。
・ペアリング
コーヒーと相性の良いマラウイ産チョコレートです。
ブラックコーヒーにはミルクチョコレート、深煎りにはハイカカオのダークチョコレートと、それぞれ絶妙なペアリングが楽しめます。
「おいしい」時間が「未来を育てる一歩」になります。
ぜひ、NPO法人せいぼの寄付型チョコレートを味わいながら、マラウイの子どもたちの笑顔に思いを馳せてください。