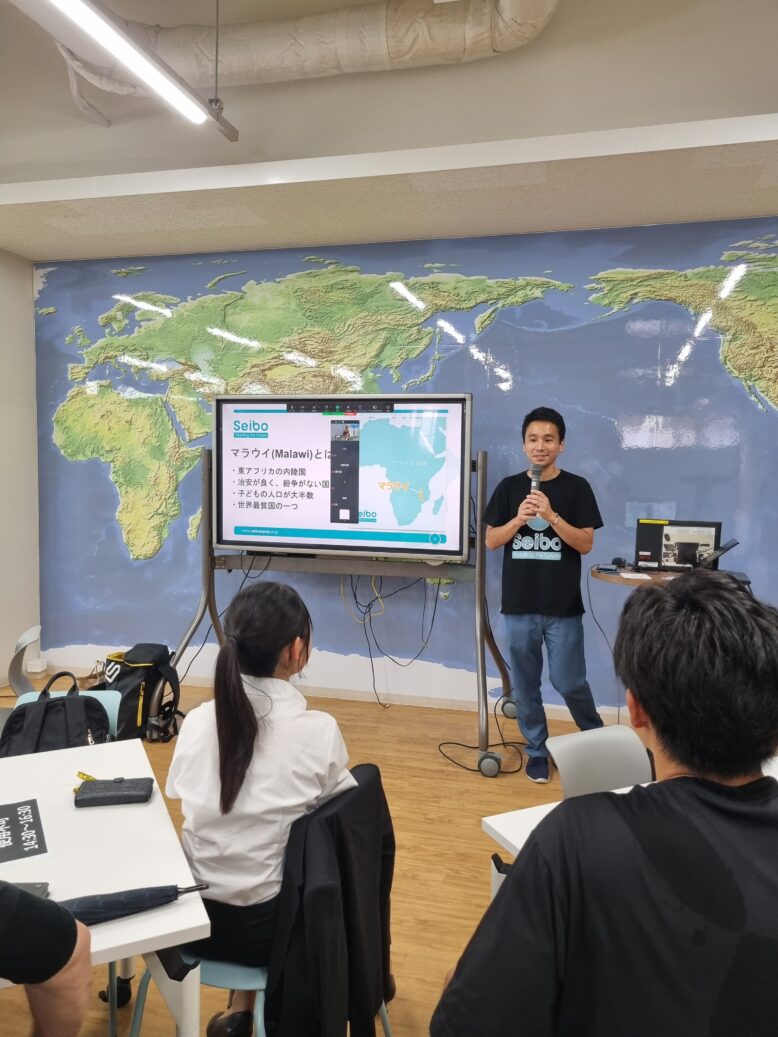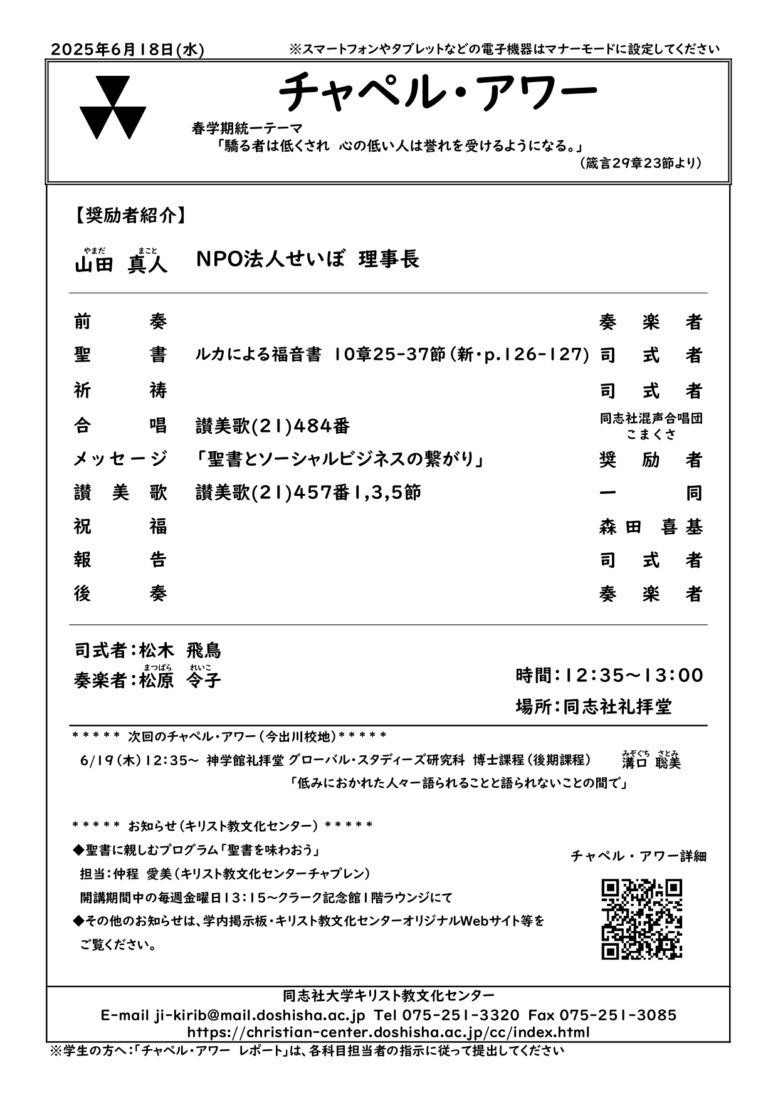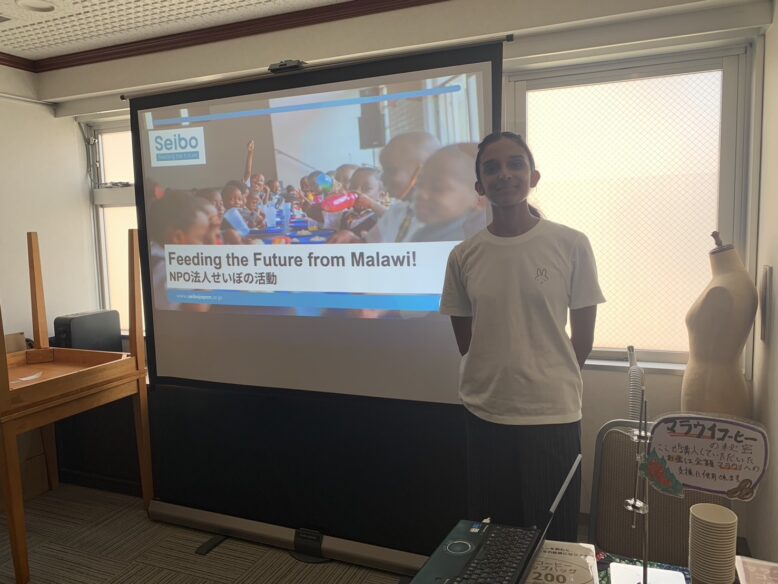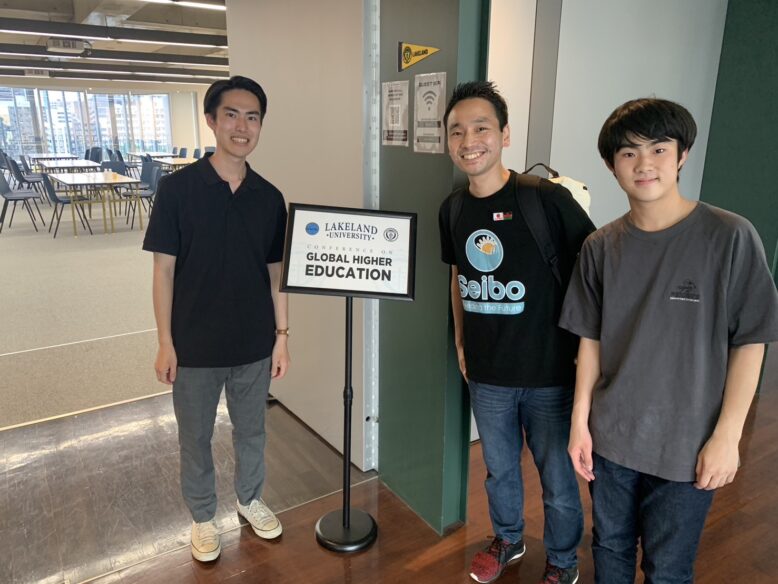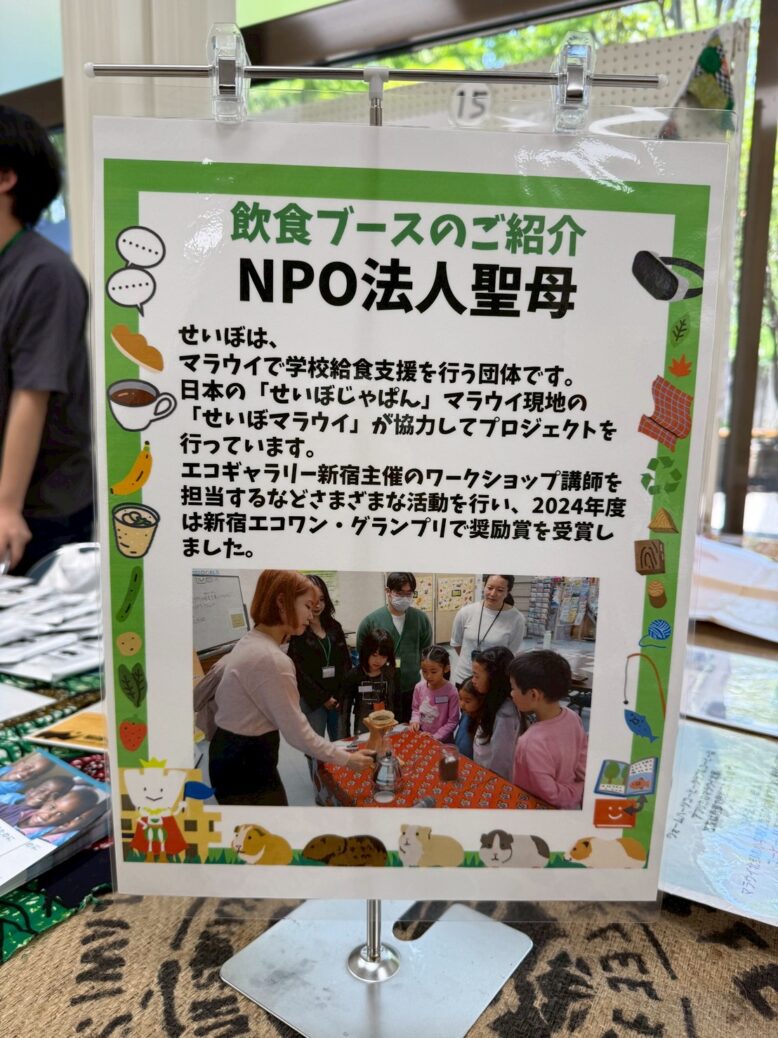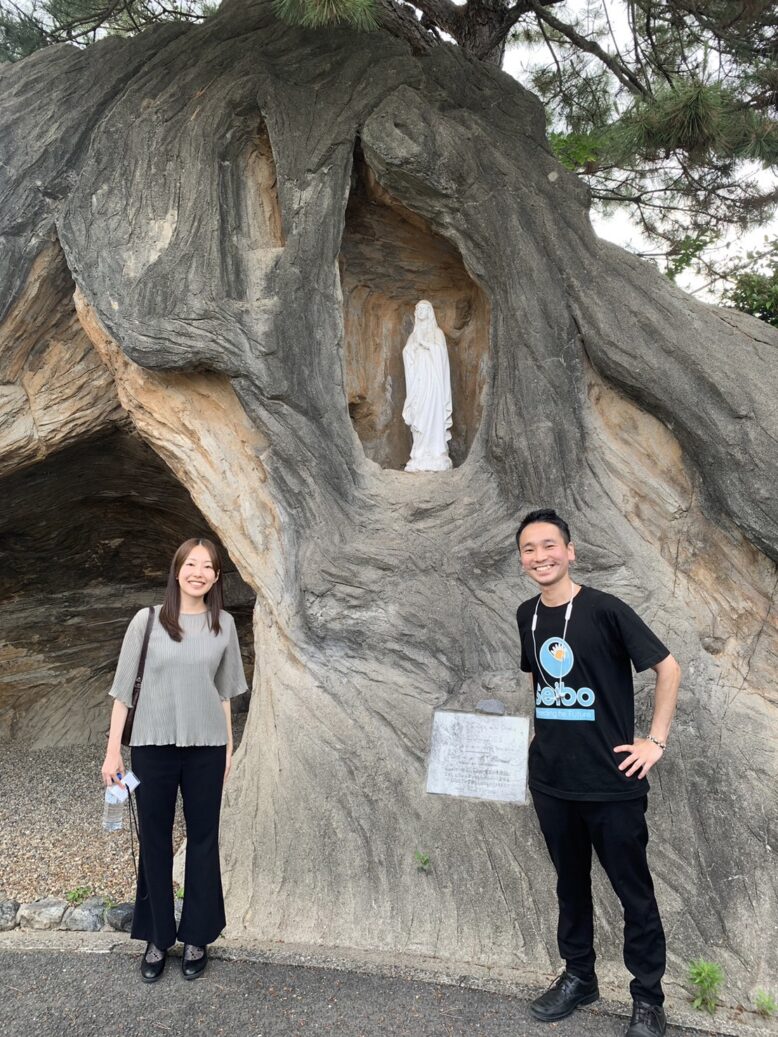1.ムジンバ地区
①Mzimba LEA(ムジンバ LEA)小学校
こちらの生徒はムジンバLEA小学校に在籍する3年生です。彼女の明るい笑顔は、学校給 食プログラムを通じて受ける栄養と支援を映し出しています。
彼女の母親は、校長を通して、このような心のこもったメッセージを伝えました 「年上の兄弟たちを育てているときはしばしば栄養失調によって病気になってしまったため に苦労しましたが、現在彼女を育てているときは滅多に病気になりません。これは学校で 食べるおかゆのおかげだと実感しています。」
せいぼの給食支援活動によって、子どもたちのみならず家族にもいい影響があるのです。
②Matewu(マテウ)小学校
マテウ小学校に通うこの生徒は、毎日しっかり欠かすことなく給食を受け取っています。彼 女は学校に通い始めたばかりですが、すでにとても楽しんでいます。 数年前の給食プログラムが導入される前、このような幼い子どもたちを学校に通わせ続け るのは、低学年においては特に困難なことでした。
かつては多くの子どもたちが学校生活に慣れるのに数週間、時には数か月もかかってい ました。しかし、給食プログラムの導入によって、その状況は大きく変わりました。 毎朝、温かいおかゆが待っていると分かっているので、子どもたちは今では学校に行くこと を楽しみにしており、未就学児にとっても同じことです。
おかゆは子どもたちの身体を養うだけでなく、学習することへのワクワク感にも火をつける のです。

マテウ小学校では、せいぼの学校給食プログラムによって、生徒たちは生活する上での衛 生習慣を身に着けつつあります。
おかゆが配られる前に、児童たちはプログラムから提供されたバケツと石けんを使って手 を洗い、自分のカップを洗います。このシンプルながらも大切な習慣は、今では彼らの学校 生活に深く根付いています。
教師たちは誇らしげに、生徒たちが衛生意識を高め、今では自宅でも食事の前に手や食 器をきれいにする習慣を身につけたと報告しています。
栄養と衛生に関する教育を通じて、私たちのプログラムは若い世代により良い健康と責任感を育んでいます。

③JICA隊員のマリコさんの訪問
5月初旬、せいぼはサリマ地区病院で保健担当官として活動しているJICAの日本人ボラン ティア、マリコさんをお迎えする機会がありました。保健と栄養の専門的な知識を持つマリ コさんは、せいぼの学校給食プログラムがもたらす栄養面での利点に強い関心を示し、さ らに詳しく知るための視察をしました。
5月4日にムジンバに到着し、5月5日から7日にかけて、私たちは毎日3校ずつ、合計9校を 一緒に訪問しました。学校訪問初日の5月5日には、マリコさんに加え、ムジンバを拠点とす るNGO、ISAPHに所属する日本人の萩原愛美さんも同行しました。 彼女たちの存在は、地 域で活動する開発パートナー間における協働と学び合いの精神を強く印象づけました。マ リコさんは、各校の訪問を通じて積極的に意見交換を行い、熱心に現場の様子を観察して いました。 マリコさんは、生徒たちとの交流を楽しみながら、おかゆを配膳し、ともに座って 食事の時間を過ごしました。
また、彼女はボランティアの調理スタッフとも時間を共にし、温 かい会話を交わしながら、彼女たちの日々の業務について理解を深めていました。ある学 校では、通常はボランティアスタッフが行う薪割りにも挑戦し、このプログラムに対する彼女 の深い敬意もうかがえました。
最終日、マリコさんは3校で簡単な栄養指導を行い、子どもたちに「健康や学びのために しっかり食べることの大切さ」を伝えました。彼女は今回の経験をとても楽しめたと語り、現 在ボランティアとして活動しているサリマ地区でも、同様の学校給食支援活動を導入したい という思いを共有してくれました。
今回の訪問は、せいぼの活動の意義と影響力を改めて印象づけるとともに、今後さらなる 連携やモデルの展開の可能性を拓くきっかけとなりました。

カプータ小学校でマリコさんが薪割りをする様子

カプータ小学校でおかゆをかき混ぜるマリコさんとマナミさん

カプータ小学校でおかゆを食べるマナミさんとマリコさん

ムジンバLEA小学校でおかゆを提供する様子

カゼンゴ小学校とセントポールズ小学校で栄養について話すマリコさん

マチェレチェタ小学校の訪問

学校訪問最終日にせいぼムジンバチームと記念撮影するマリコさん
④日本大使館からの訪問
5月20日、日本大使館から鈴木さんとHugo Mlewaさんが、草の根・人間の安全保障無償資 金協力(GGP)の現地確認プロセスの一環として、せいぼのムジンバ事務所を訪問しまし た。今回の訪問では、マチェレチェタ小学校、チャベレ小学校、カニェレレ小学校の3校にお ける調理施設建設案の評価が目的でした。現地視察では、調理環境の改善が明らかに必 要であることが認識されました。お二人からは前向きなご意見をいただき、助成金申請に 対する良い結果を期待しています。

カニェレレ小学校での様子
学校給食プログラムの効果的な運営には、関係者の連携が欠かせません。
正確な帳簿記録の重要性についても強調されており、オフィス職員、保護者、そして学校長の全員がそれぞれの役割を適切に果たすことが、プログラム成功の鍵となります。

(写真はティブイラネ写真は幼稚園)

学校で子どもたちに食事を提供するだけではなく、マラウイの未来を担う世代に対して、栄養価が高く温かい食事を安定的に届けることが重要なのです。
現場の担当職員として、常に高い基準でおかゆを調理することは、スタッフの最優先事項です。(写真はティナシェ幼稚園)

子どもたちに食事を届けることは、私にとって本当にやりがいのある経験です。
食事を目にして目を輝かせる子どもたちの表情を見た瞬間、胸が温かくなり、喜びに満たされます。
(写真はティナシェ幼稚園)

毎日栄養価の高い食事を準備するには、調理スタッフの高い献身と責任感が求められます。
おかゆを配膳する際に見せる子どもたちの笑顔や生き生きとした様子が、その努力に何よりの報いを与えてくれるのです。(写真はティナシェ幼稚園)

学校委員会や保護者は、ステークホルダー会議に積極的に参加し、地域との関わりを深めるとともに、給食プログラムの効果と持続可能性を支えるために、それぞれの責任を再確認しています。 (写真はチリンガニCBCC、5月8日)

委員会のメンバーは、調理作業を保護者や調理スタッフに任せきりにするのではなく、自らも積極的に関わり、たとえば井戸から清潔な水を汲むといった活動にも参加しています。
こうした取り組みにより、常に安全な水が使用され、衛生基準の維持につながっています。
(写真はチリンガニCBCC、5月19日)

何よりも、炊きたてのおかゆの香りと、おいしい食事によって満たされた幸福感こそが、子どもたちの笑顔を引き出しているではないでしょうか。 (写真はマクウィカ幼稚園)
給食支援データ(5月)
合計支援給食数:330,974食
北部ムジンバ地区:290,278食
南部ブランタイヤ地区:40,696食