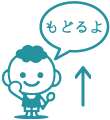2025年8月30日、せいぼはカトリック教育学会にて研究発表を行いました。
カトリック学校で育まれる「隣人を大切にする心」や「社会に役立ちたいという思い」。これらの価値観は、実は教室の外で大きな力を発揮します。今回の発表では、NPO法人せいぼの活動を例に、教育現場と社会活動が結びつくことで生まれる学びの意義を紹介しました。特に大学でのキャリア教育との関わりは、学生たちの成長を後押しする大切な機会となっています。
1. 教育現場とNPOがつながるとき
カトリック教育は「思いやり」「社会正義」「奉仕」を大切にします。ですが、授業だけでは実際の経済や社会課題に触れる機会は限られています。そこで役立つのが、NPO法人せいぼのような団体です。せいぼは、給食支援やフェアトレードを通して、学生が学んだ価値観を「社会の中で実践する場」を提供しています。
2. 経済を通じて学ぶ社会の仕組み
NPOの活動には「経済」の視点も欠かせません。例えば、せいぼが販売するマラウイ産コーヒーは、単なる商品ではなく、途上国の暮らしや公正な貿易の仕組みを知るきっかけになります。
学生たちは、NPOはボランティアとは違い、利益を生み出しつつも、それを社会的な目的に優先的に使うという仕組みを学びます。これは教皇フランシスコが語る「貧しい人への優先的選択」にもつながる学びです。
3. 高校での取り組み

・聖園女学院中学高等学校
生徒たちはマラウイ産コーヒーや紅茶の販売・広報活動を通じて、社会課題へのアプローチを体験しました。さらに姉妹校・南山大学の先輩学生と交流し、価値観を「高校から大学へ」とつなげる学びを深めています。
・光ヶ丘高等学校
マラウイ人スタッフへのインタビュー、NPOの理事会参加、大阪万博でのスタッフ活動など、国内外をつなぐ経験を重ねています。社会に実際に関わるリアルな体験が、生徒たちの視野を大きく広げました。
4. 大学での取り組み
大学では、こうした学びがキャリア教育としてさらに広がります。インターンシップやボランティアを通じて、自分のキャリアの可能性を描く学生が増えています。
特に南山大学や立教大学では、ボランティアセンターを通じて多くの学生がせいぼで活動しています。その中には、有給スタッフとして中心的に関わり、将来はNPOや社会貢献に関わる仕事を目指す学生も少なくありません。
5. 協働が広げる可能性
せいぼの取り組みは、カトリック学校との連携だけにとどまりません。立教大学のようにキリスト教の精神を大切にする学校とも協力し、宗派を超えて社会に広がる活動を生み出しています。共通の「人を大切にする」という価値観が、多様な連携を可能にしています。
まとめ
カトリック教育とNPOの協働は、学生に「社会とつながる実感」を与えます。そして、自分の存在や学びがどのように社会に役立つのかを考えるきっかけとなります。
NPO法人せいぼの活動事例からは、教育の場で培った価値観が経済や社会活動の中で活かされる可能性が見えてきました。こうした取り組みは、これからのキャリア教育にとっても重要な道しるべとなるでしょう。