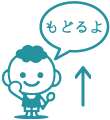はじめに
2025年6月17日から20日の4日間、マラウイ共和国(以下、マラウイ)のヴィトゥンビコ・ムンバ貿易産業大臣(H.E. Eng. Vitumbiko Mumba:以下、ムンバ大臣)が訪日されました。執筆時点(2025年8月26日)において、ムンバ大臣は現政権のチャクウェラ大統領から2025年9月の大統領選挙に向けて副大統領候補に指名されており、将来を嘱望されている人物です。
今回の訪日の主な目的は、大阪で開催中の万国博覧会(以下、万博)において、6月18日に行われた「マラウイ・ナショナルデー」への出席でした。ナショナルデーとは、万博の公式参加国に1日ずつ割り当てられる日で、各国の文化や伝統を紹介する催しが行われます。
筆者は現在、上智大学国際教養学部4年生であり、マラウイの小学校や幼稚園等で学校給食支援を行うNPO法人せいぼ(以下、せいぼ)のスタッフとして活動しています。せいぼは今回の万博開催にあたり、駐日マラウイ大使館よりマラウイ・パビリオンでのスタッフ派遣を依頼されていました。
そのような中、光栄なことにムンバ大臣の訪日期間4日間にわたり、リエゾンおよび日英通訳として随行する機会をいただきました。リエゾンとしての役割は、大臣・大使館・万博運営・その他関係者との橋渡しを行い、訪問スケジュールの調整や必要な情報共有を円滑に進めることです。本稿では、その経験を文章と写真を通じて記録・報告いたします。

6月18日の晩餐会時の大臣と筆者
訪日記録(2025年6月17日〜20日)
準備
ムンバ大臣の訪日に先立ち、JTB儀典部、外務省、大阪万博運営事務局、駐日マラウイ大使館との打ち合わせを行いました。リエゾンとしての主な役割は、日程や車列の導線管理、関係各所との調整、ならびに日英通訳でした。また、マラウイ投資貿易センター(MITC)のプレゼンテーション資料の翻訳作業も担当しました。
6月17日(火)
関西国際空港にてムンバ大臣を出迎え、宿泊先ホテルまでご案内しました。到着後にはホテル側リエゾンと打ち合わせを行い、翌日の動線や式典スケジュールを確認しました。大臣の私的なご要望として、散髪への同行や大臣夫妻の食事の選定も対応しました。
6月18日(水)〈ナショナルデー当日〉
ナショナルデー当日は、早朝にホテルへお迎えに上がり、車列で万博会場へ向かいました。出発が少し遅れたため到着がぎりぎりとなりましたが、迎賓館にて三澤日本国際博覧会政府代表代理による挨拶を受け、簡略式の呈茶が行われました。その後、公式式典に臨み、三澤代理のスピーチに続いてムンバ大臣が登壇されました。大臣は日本との協力関係強化に触れつつ、農業・観光・鉱業・製造といった未活用分野での投資の可能性について訴えられました。式典後には、マラウイ国立舞踊楽団による伝統舞踊が披露され、会場は大いに盛り上がりました。
 ナショナルデー公式式典の様子(筆者撮影)
ナショナルデー公式式典の様子(筆者撮影)
式典終了後の午餐会では、大臣夫妻、クワチャ駐日大使夫妻や元在マラウイ日本大使、日・マラウイ政府関係者、そしてその他マラウイに深く関わっていらっしゃる企業・団体・研究者の方々が列席しました。この午餐会では、リエゾンという立場からではなく、マラウイに関わる団体の一員として、NPO法人せいぼの職員という立場で参加者として同席させていただきました。

午餐会での一幕(筆者撮影)
午後には日本館、自国のマラウイパビリオン、韓国館、オーストラリア館を視察し、各国の展示を通じて文化や技術に触れる機会がありました。その後、一行はホテルに戻り、短い休憩を取りました。
また、大臣とは別会場では、マラウイ投資貿易センター(MITC)の長官であるクルーガー氏が登壇し、マラウイの投資・貿易分野におけるポテンシャルについてのプレゼンテーションが行われました。この場では、せいぼ代表であり理事長の山田真人氏が通訳を務め、日本の参加者に向けてマラウイ経済の可能性を直接伝える役割を果たしました。大臣のパビリオン訪問と並行して行われたこの取り組みも、マラウイの「未活用分野」への投資を呼びかける重要な発信の一つでした。

MITC長官クルーガー氏によるプレゼンテーション(写真:MBCより)
夜にはマラウイ政府主催の晩餐会が開催され、国内外からの来賓が集いました。晩餐会では、大臣自らがマラウイの魅力と日本との協力関係の可能性について繰り返し言及し、文化交流と経済交流の両面で関係を深める場となりました。
6月19日(木)
この日は朝、ホテルから新大阪駅へ向かい、新幹線で東京駅に到着しました。東京のホテルにチェックイン後、公式訪問が続きました。
最初の訪問先は、アタカ通商株式会社でした。アタカ通商は世界各国のスペシャルティコーヒーを専門とする日本の商社で、せいぼの学校給食支援活動に共感いただき、せいぼの運営するWarm Hearts Coffee Clubにコーヒーを提供していただいております。会談では、マラウイ産品の輸出や日本市場における新たな貿易機会について意見交換が行われました。企業としての具体的な関心や課題が提示され、今後のビジネス協力の可能性について議論がなされました。

ムンバ大臣とアタカ通商荒木社長(写真:駐日マラウイ大使館より)
続いて、国際連合工業開発機関(UNIDO)東京投資・技術移転促進事務所(ITPO Tokyo)を訪問しました。ここでは、マラウイにおける投資環境や産業開発の可能性が紹介され、日本企業に向けた投資誘致のための協力について話し合いが行われました。
午後には、国際協力機構(JICA)を訪問しました。JICAとの会談では、インフラ整備や農業開発、人材育成といった分野におけるマラウイへの協力の現状と今後の展望について意見が交わされました。教育や農村開発を通じて持続的な経済発展を支える取り組みについても触れられました。

JICA訪問の様子(筆者撮影)
最後に、駐日マラウイ大使館を訪問しました。ここでは、大使館職員との打ち合わせを行い、今回の訪日全体を通じての調整や総括的な意見交換が行われました。
その後、大臣をホテルまでお送りし、この日の行程は終了しました。
6月20日(金)
午前はエネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)を訪問し、理事やアフリカ地域担当者らとの面談が行われました。当初予定されていたその後の経団連訪問は中止となりました。その後、ホテルから空港へ移動し、帰国の途につかれました。
おわりに
今回の訪日を通じて、ムンバ大臣が繰り返し強調されていたのは「未活用分野(untapped opportunities)に日本の力を」という呼びかけでした。具体的には農業、観光、鉱業、製造といった分野での協力の可能性が挙げられ、日本の企業や機関がマラウイに進出する余地は大きいと訴えられていました。このメッセージは、会談やスピーチの場で繰り返し耳にしたものであり、現チャクウェラ政権が「ATM+M(Agriculture, Tourism, and Mining + Manufacturing)戦略」として掲げている国家戦略と一致しています。現場で直接聞いた言葉が外部にもそのまま届けられていることを確認し、大臣の発信の一貫性と重みを実感すると同時に、リエゾンとしてその場に立ち会えたことを光栄に感じました。
4日間を振り返ると、通訳、リエゾンという二つの役割を背負い続ける濃密な日々でした。学生としては決して体験できないような貴重な機会であり、どのような要望や予定変更があるか分からない中で、常に緊張感を持ち続ける必要がありました。時間の遅れや空港でのトラブルなど難しい場面もありましたが、それらを乗り越える中で大きな充実感を得ることができました。マラウイという国への理解と興味も一層深まり、今後のせいぼの活動に向けたモチベーションにもつながっています。
最後に、この経験を支えてくださった全ての関係者に心から感謝申し上げます。大臣をはじめとする代表団の皆様、大使夫妻を含む大使館職員の方々、万博運営スタッフ、外務省担当職員、JTBエスコート、そしてその他全ての関係者のお力添えがあったからこそ、今回の任務を無事に果たすことができました。ここで感謝を述べるとともに、本稿の締めとさせていただきます。

ホテルニューオータニにて筆者
本稿のPDF版はこちらよりご覧ください
関連リンク
晩餐会の様子(Malawi Broadcasting Corporation: MBC)
https://fb.watch/BaJKOeV3WJ/
ナショナルデー記事(MBC)
Malawi showcases investment opportunities at Osaka Expo 2025
ナショナルデーの様子(駐日マラウイ大使館)
MALAWI NATIONAL DAY CELEBRATED AT EXPO 2025 IN OSAKA, JAPAN.
日本館・韓国館・オーストラリア館訪問の様子(駐日マラウイ大使館)
アタカ通商とのミーティング(駐日マラウイ大使館)
THE MINISTER OF TRADE AND INDUSTRY’S MEETING WITH ATAKA TRADING CO., LTD.
JICAとのミーティング(駐日マラウイ大使館)
国際連合工業開発機関[UNIDO]とのミーティング(駐日マラウイ大使館)
THE MINISTER OF TRADE AND INDUSTRY’S MEETING WITH UNIDO ITPO.
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構[JOGMEC]とのミーティング(駐日マラウイ大使館)
6月18日は『マラウイ』のナショナルデー! みんなでマラウイの特別な日を一緒に迎えましょう(大阪・万博博覧会2025公式サイト)
https://www.expo2025.or.jp/officialblog/nd_0618/